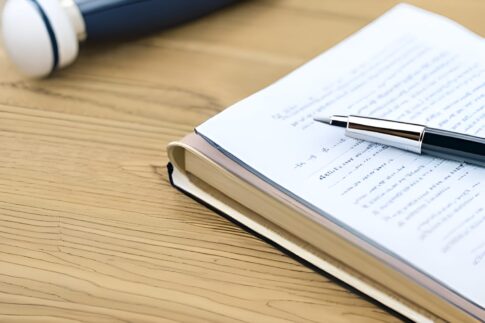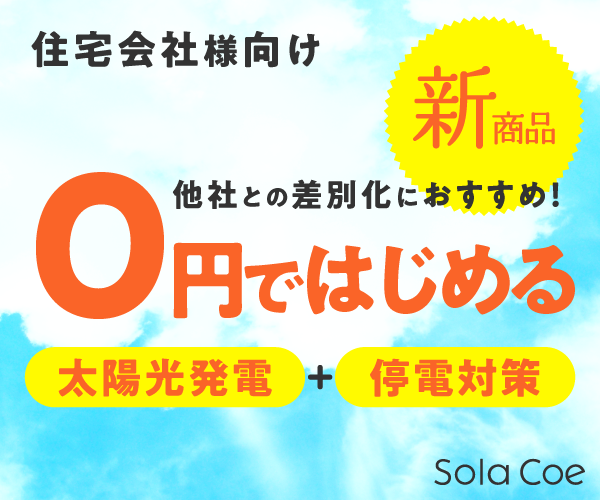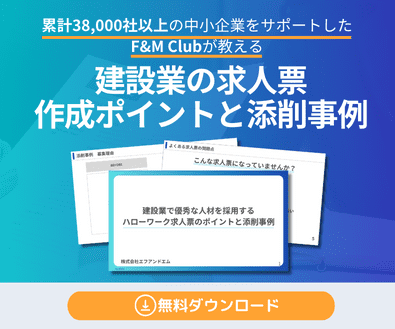工務店が工事を受注する場合、工事請負契約書の作成が欠かせません。
しかし、工事請負契約書を作成せずに、注文書と注文請書のみで済ませている工務店は少なくありません。
この記事では、工事請負契約書がないとどうなるのか解説します。
また、作成しない場合のリスクについても合わせて取り上げているため参考にしてください。
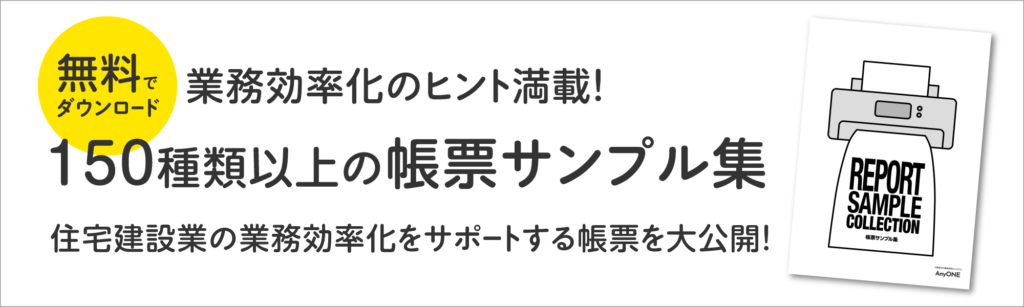
目次
工事請負契約書の役割と記載項目

工事請負契約書とは、工務店が工事を受注する際に発注者との間で契約を結ぶために使用する書類のことです。
工事請負契約書は工事の基本となるものであり、発注者・受注者それぞれの名前をはじめとして、工事の期間、工事の内容、請負代金の額などの記入必須項目と、そのほか工事ごとに記載が必要な内容を記載します。
工事請負契約書があれば、工事内容に関して不明確な部分がなくなるため、発注者との認識の違いからトラブルが発生する恐れがありません。
また、発注者と受注者との間で請負契約の片務性が発生することもないため、工務店が損害を被るといったケースも発生しないでしょう。
なお、実際に契約を結ぶ場合、工事請負契約書を用意するだけでなく、工事請負契約約款や設計図書などそのほかの書類も用意する必要があります。
詳しくは工事請負契約書について解説している記事をご覧ください。
工事請負契約書がないと法律違反

工務店が工事を受注する際に、工事請負契約書を作成しないと法律違反となります。
建設業法条第十九条第一項では、契約書は原則として工事の着工前に交付しなければならないと定められています。
請負契約の明確性と正確性を担保して、紛争を防止するためです。
建設業法 第十九条 (建設工事の請負契約の内容)
第一項 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
【引用】建設業法 第十九条第一項-e-Gov法令検索
工事が始まってから急いで作成するのではなく、とにかく着工前の段階で作成するようにしましょう。
なお、災害などによって着工前に工事請負契約書の作成ができないケースも考えられます。
このような止むを得ない場合は、必ずしも着工前までに交付しなければならないわけではありません。
ただし、基本的には、工事の前に工事請負契約書を作成し、契約を締結する必要があると考えておいてください。
また工事現場によっては、工事ごとに契約書を結ぶことが難しい場合もあります。
このような場合は、現場の状況を踏まえたうえで対応するようにしましょう。
例えば、一定期間をカバーする基本の契約書を作成し、個々の工事に関しては発生するたびに注文書・注文請書を結ぶという形にすれば、一度に全ての契約書の作成が難しい場合でも対応可能です。
作成が難しいからといって着工前に契約書を作成しないと法律違反となるため、上記のような対応を検討してみてください。
【参考】建設業法令遵守ガイドライン(第4版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点 --国土交通省土地・建設産業局建設業課
工事請負契約書がなくても契約自体は成立する
工事請負契約書を用意していないからといって、工事の請負契約自体が無効になるわけではありません。
一部の例外を除き、契約書がなくても口約束で契約は成立するとされているためです。
民法 第五百二十二条 (契約の成立と方式)
第一項 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
第2項 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
【引用】民法 第五百二十二条 (契約の成立と方式)-e-Gov法令検索
これを踏まえると「やはり工事請負契約書を作らなくてもいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかしこれは、あくまでも契約が成立しているだけであり、工事請負契約書を作成しなかったことによる違法状態がなくなるわけではありません。
また、口約束による契約となると、認識の違いが生じやすいです。
契約書とは異なり、後になってから契約内容を振り返ることができないため、トラブルにつながる可能性が非常に高いといえます。
ちなみに、契約書を作成しなかった場合、後述するような処分が下される可能性もあるため、必ず作成するようにしてください。
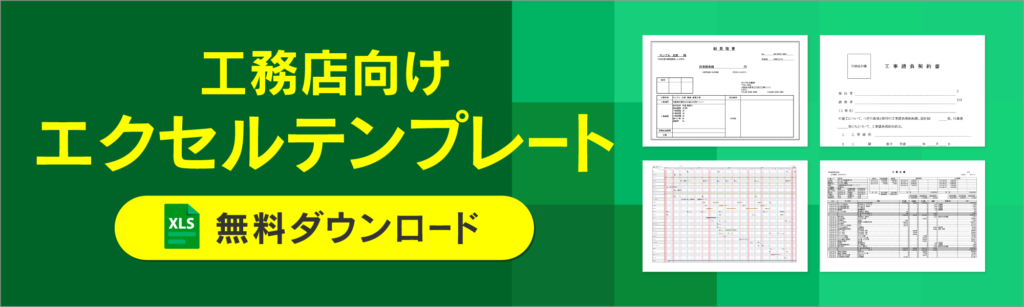
工事請負契約書を作成しない場合

工事請負契約書を作成しないと、工務店はさまざまなリスクを被る可能性があります。
場合によっては、事業の継続ができなくなる恐れもあるため注意しなければなりません。
ここでは、契約書を作成しないとどのような事態になるのか、以下の点を中心に解説します。
処分
工事請負契約書の未作成、つまり建設業法に違反した工務店は監督処分がおこなわれます。
具体的には、国道交通大臣や都道府県知事からの指導や1年以内の営業停止処分などの処分です。
また情状が重いと判断された場合は、建設業の許可の取り消しや更新不可になる可能性もあります。
そうなると、事業自体を続けられなくなるため、従業員やその家族を困窮状態に陥れてしまう恐れもあるでしょう。
また、許可取り消しなどの処分を避けられたとしても、監督処分が下された場合は、処分情報が公表されるため、その後の事業や取引などに影響する可能性が考えられます。
紛争の恐れ
建設業は、1つの工事で取り扱う金額が大きく、受発注者の間で所有する情報量に違いがあるため、紛争が起こりやすい業種であるといえます。
ただでさえ紛争が起こりやすい状況であるにもかかわらず、工事請負契約書を作成しないとなると、認識の食い違いやトラブルが発生する可能性が大いにあります。
また、そこから裁判などの紛争につながる恐れもあるでしょう。
裁判などとなると、対応するだけで費用と時間を無駄にしてしまいます。
業者を変えられてしまう
工事請負契約書を作成せずに工事をおこなうことは、建設業法違反であると同時に、発注者が工務店に対して不信感を募らせる原因となります。
発注者が工務店に対して「モラルに欠けている」など悪い印象を抱いてしまうと、最悪の場合業者を変えられてしまう恐れがあります。
企業としての評価が下がると、新規工事の受注にも影響が出る可能性があります。
まとめ
今回は、工事請負契約書の概要から、作成しないとどうなるのか解説しました。
工事請負契約書なしでの工事は法律違反です。契約自体は成立しますが、企業は処分を受けることとなります。
また、処分だけでなく紛争のリスクや業者を変えられてしまうリスクもあるため、工事請負契約書は必ず作成するようにしましょう。
工事請負契約書の作成が面倒だと感じる場合は、工事請負契約書テンプレートや建設業向けの業務効率化ソフトがおすすめです。
テンプレートの場合は、工事請負契約書と工事請負契約約款がセットになっている場合もあります。
また、建設業向けの業務効率化ソフトの場合は、他の帳票作成や工務店業務全般を効率化することも可能です。