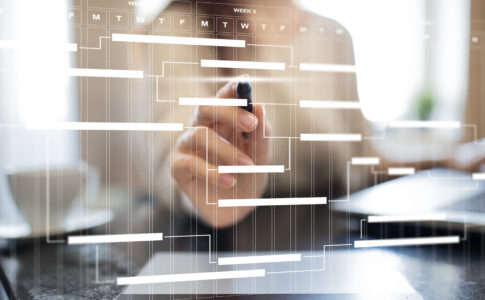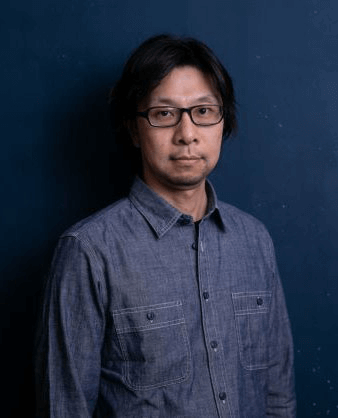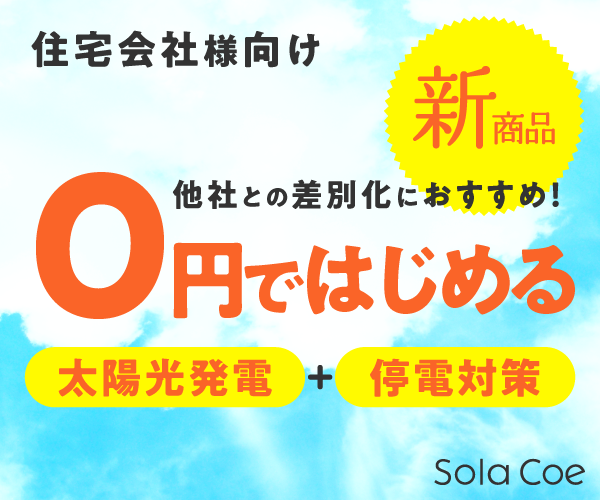工程表は、納期や生産管理に有効な進捗状況を把握できる表です。
この記事では、工程表の概要や種類と特徴、作り方の手順と見やすい工程表の作り方を解説します。
工程表の書き方にお悩みの方は、ご一読ください。
目次
工程表とは

工程表とは、土木・建設などの工事の複数作業の進捗確認に使われる表です。
工程表には、主にに以下のような内容を記載します。
工程表の種類は主に3種類ありますが、どれも工程の進捗管理やタスクの把握に優れています。
よく使われる工程表の種類と特徴
建設現場でよく使用される工程表は、3種類あります。
- ガントチャート
- バーチャート
- ネットワーク工程表
工程表の種類ごとに特徴があるため、現場の工程や何を最も把握したいのかを考え、工程表を選ぶことが大切です。
それぞれの工程表の特徴や得意分野、管理しにくい部分を解説します。
ガントチャート
ガントチャートは、縦軸に作業内容や担当者を入力し、横軸に進捗状況を記載していく工程表です。
複数の作業を同時進行させる際に向いている管理方法で、特殊な記号などを使わないため、誰でも作成・記入ができるのが特徴といえます。
また、直感的に理解がしやすく、作業がどこまで進んでいるかを誰でも理解できるでしょう。
MicrosoftエクセルやGoogleスプレッドシートなど、すでに手元にあるツールで簡単に作成できます。
デメリットは、作業同士の関連性を把握しづらく、作業手順が複雑かつ相関関係にあることが把握しにくい点です。
ガントチャートについては、以下の記事でも詳細に説明しているため、参考にしてみてください。
バーチャート
バーチャートとは、縦軸に作業内容を入力して横軸に日付を入れる表です。
ガントチャートに似ていますが、複数作業の可視化と日程管理に優れる表といえます。
バーチャートを用いると、「複数作業にどの程度の日数と日程が必要なのか」を一覧で確認できます。
デメリットは、ガントチャートと同様に作業同士の関連性を把握しにくいことでしょう。
単純に、複数作業が同時進行する現場向きのチャートです。
バーチャート工程表については、以下の記事で詳しく解説しています。
ネットワーク工程表
ネットワーク工程表とは、番号や矢印などの記号を用いて内容と日数を管理する工程表です。
バーチャートやガントチャートでは管理しにくい、相互関係がある作業の管理に向いています。
ただし難点は、記号などを用いるため工程表自体が複雑になりやすく、作成者・管理者が限定されることです。
また、読み取りにも知識が必要なため、作業員全員が工程表を理解できないかもしれません。
ネットワーク工程表を使うべき場面や作り方については、こちらをご参照ください。
工程表の活用で納期・生産管理を効率化

工程表を作って進捗確認をおこなうと、納期を厳守して生産管理をおこなえるでしょう。
スケジュールの管理は特に大事で、納期の厳守によって取引先との信頼関係を築けます。
万が一、納期に遅れれば、先方の引き渡し予定などにも影響を与え、損害を発生させるためです。
また、生産管理をしっかりおこなえば、コスト削減や必要機材の把握、生産性の向上に役立ちます。
工程表を見やすく工夫すれば、従業員にも工程が伝わりやすくなり、スムーズな工事の実現も可能です。
工程表を書くときの3つの注意点

工程表を書く場合に注意したいポイントを3つ紹介します。
ただ無作為に作業内容と日程を書いただけでは、工程表の意味がありません。
作業を管理する目的を忘れないようにし、注意点を意識して工程表を作りましょう。
作業員同士の共有方法
工程表作成後に、どうやって現場作業員に共有するかも考えておきましょう。
建設DXが進んでいる企業なら、タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末で共有可能です。
しかし、またモバイル端末の配布などが進んでいないなら、印刷して現場に持ち込む、または朝礼で共有する方法がメインとなります。
せっかく進捗管理をしても、作業員にも内容を伝達できないと意味がありません。
効率よくいつでも工程表を管理できる仕組みが必要なら、事前にシステム導入の検討も必要です。
工程表の管理ルール
工程表を作成したら、その後どのように管理していくかを決めましょう。
複数名が誰でも入力・変更できるようにすると、内容を誤って入力・削除してしまうリスクが高まります。
また、入力時に各々が好きな色をつけるなどすると、表に統一性がなく、わかりにくい工程表になってしますはずです。
工程表をどのように運用するかのルールは、事前に決めてください。
作業員が理解できる見やすい表の選択
工程表を選ぶときは、作業員全員が直感的に理解できるものを選びましょう。
複雑な工程表の1つであるネットワーク工程表を使う際は、記号の読み取りの一覧を作成して共有するなどの工夫が必要です。
工程表を作る目的は、現場作業員がそれぞれ進捗を把握して、当事者意識と納期への意識を高めることです。
誰でも簡単に理解できる工程表を目指し、工程表を作りましょう。
見やすい工程表の書き方

工程表の書き方の手順を解説します。
適切な工程表を作るには、事前の施工範囲の設定やタスクの洗い出しなどの準備が重要です。
作業員が理解しやすく、またきちんと工期を把握できる工程表を作るために手順をおさらいしましょう。
施工の範囲と手順・タスクの洗い出し
まずは工程表に書き込む施工の範囲と手順を書き出し、タスクをすべて洗い出しましょう。
抜けがあると正しく工程管理できません。
施工の全手順が入るように、工程表作成前にすべて書き出しましょう。
施工期間の設定
タスクの洗い出しが終わったら、それぞれの作業に対して施工期間を設定します。
施工期間は納期に間に合うようにすることはもちろん、無理のないように設定しましょう。
無理のある期日を設けると、作業員に心理的なプレッシャーがかかります。作業が荒くなって、最終的に施工のやり直しを求められるかもしれません。
また、急な病欠やトラブルが発生した際に、納期ギリギリでは他の作業との釣り合いや調整が難しくなるはずです。
施工期間は余裕を持ち、無理がないよう振り分けしてください。
担当者の振り分け
期間が決まったら、担当者を振り分けていきましょう。
まずは作業人員を把握して、作業ごとに分担します。
1人の人員に作業が偏ったり、逆に割り当てのない人員が出ないように、最終チェックしてください。
作業の偏りは、長時間労働や過労の原因となります。
工程表に割り振る人員を事前にリスト化し、各々の作業量をチェックしてください。
工程表の種類の決定
最終的にタスク・日程・人員を書き出してから、工程表の種類を決定しましょう。
ガントチャートやバーチャートは、タスクの可視化と日程管理に役立ちます。
複雑な工程を管理したい場合は、ガントチャートやバーチャートでは管理しにくいため、ネットワーク工程表が望ましいです。
工程管理で何を優先したいのか、施工の種類や複雑度によって工程表を決めてください。
見やすい工程表を簡単に作成する方法

最後に工程表を簡単に作成する方法を紹介します。
工程表の管理方法や効率的な使い方がわからない方は参考にしてください。
手書き
最も簡単でコストもかからないのが、工程表を手書きする方法です。
模造紙などに工程表を書いて、その図面を印刷してホワイトボートや手渡しして共有します。
メリットはシステムやエクセルソフトの導入費用などがかからず無料であること、誰でも取り組めることです。
しかし、難点として紙の印刷コストがかかること、手書きのため修正が難しく最終的にわかりにくい管理表になる可能性があります。
また共有がしにくく、管理表を持ち運ぶ不便さがデメリットです。
エクセル・スプレッドシート
すでにオフィスソフトを導入しているなら、エクセルを使って工程表を作成できます。また、スプレッドシートはオンラインで無料で工程表を作成できるでしょう。
ガントチャートやバーチャートのテンプレートを利用すれば、特別なスキルや知識がなくとも、直感的に工程表を作成できます。
スプレッドシートはクラウド上で作成できるため、モバイル端末を配布している工務店なら共有も簡単です。
デメリットは、複雑な工程表が作りづらく、また共有設定を誤ると機密情報の漏洩リスクがあります。
また数式を用いる場合は、関数の知識を持った人員が必要となり、管理者が限られて属人化しやすいこともデメリットです。
管理運用のルールをあいまいにし、誰でも入力できるようにしておくと、作った工程表データが壊れるかもしれません。
専用システム
手書きやエクセル・スプレッドシートによる工程管理のデメリットを補える「専用システム」の利便性は高いです。
工務店専用のシステムを導入すれば、工程表の作成が簡単にできます。
また、さまざまな機能を集約したオールインワンシステムなら、工程管理以外にも受発注管理や書類申請、図面管理も可能です。
オンラインで使用できるため、作業員がモバイル端末からいつでも進捗の確認ができることもメリットでしょう。
ただし、導入コストがかかることや操作方法を覚えるまでに、研修の手間や時間がかかることはデメリットです。
そこでおすすめしたい工務店向けシステムが「AnyONE」です。
エクセルと似た操作感で、直感的に工程表を作成しやすい点が特徴で、図面管理や受発注管理も一元化できます。
導入後のサポートも充実しており、システムの操作方法がわからない場合もすぐに問い合わせができるでしょう。
まとめ
工程表の活用は、納期厳守だけでなく生産管理にも役立ちます。
人員の割り振りの見直しにも役立ち、効率化や業務負荷の軽減にも繋がり、労働環境の改善も期待できるでしょう。
工程表にはいくつか種類があり、それぞれのチャートで管理しやすい点が違います。
まずは、工程表の種類を理解してから、タスクや人員を洗い出して工程表を作成してみましょう。
工程表作成の際は、手書きやエクセル・スプレッドシートを利用する方法もありますが、専用システムがおすすめです。
建設DXを推進している現在の業界の流れを見ても、数年のうちにシステムの切り替えが必要となります。
建築現場博士がおすすめする工務店・建築業界の業務効率化ソフトはAnyONEです。
導入実績2,700社超の業界No.1基幹システムで、国交省「第一回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択されています。
エクセルのような操作感で、レイアウトもマウスで変更できるため、ITが苦手な方でも簡単にお使いいただけます。
また、システムの導入後も徹底的なサポートを受けられるため、安心して運用できるでしょう。
大手・中堅企業様から一人親方様まで規模感を問わず、業務状況に合わせて様々な場面でご利用いただけます。