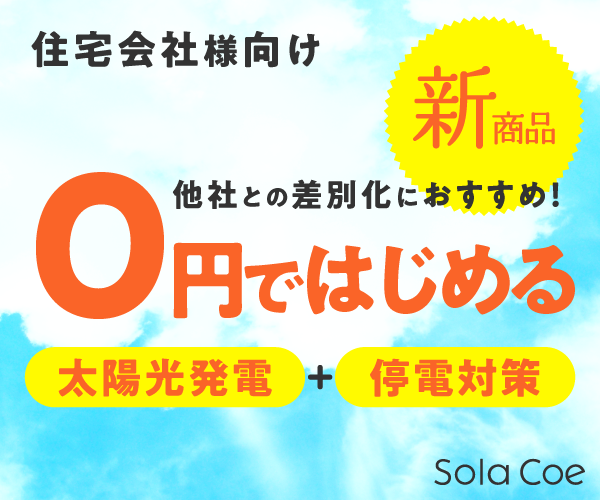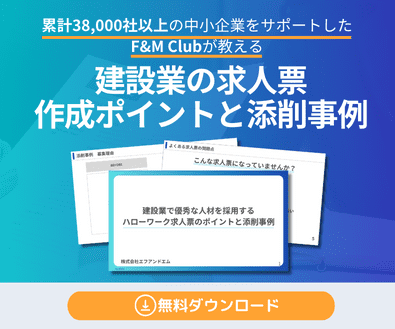工務店の集客方法の1つとして、チラシの配布を検討している工務店経営者は多いのではないでしょうか。
しかし下記の悩みがあり、チラシの作成に着手できていない方もいるでしょう。
- チラシの作成経験がない
- チラシ作成に予算を割けない
- 特殊なツールを購入しなければならないのでは?
上記の方におすすめなのが、無料テンプレートの活用です。
本記事では、工務店がチラシをで集客するメリット・デメリット、無料テンプレートの使い方を解説します。
チラシでの集客を考えている工務店経営者は、ぜひ最後まで読んでください。
目次
【工務店】チラシの効果

ここでは、チラシを作ることに関して、メリットとデメリットを紹介します。
チラシのメリット
チラシをメリットは、配布するエリアを指定できることです。
配布エリアが指定できれば、ローカル色を出せより尖った内容を記載できます。
例えば、以下の表現が考えられます。
- スーパー〇〇の隣:立地を説明する際に記載
- △△町の方限定:サービスを紹介する際に記載
チラシの配布エリアを限定すると、その地域に住んでいるからこそわかる説明の仕方が可能です。
またチラシは、普段からネットで情報収集をおこなわないお年寄りに情報を届けられます。
例えば、下記のようなお年寄りの悩みを解決できる情報の記載がおすすめです
- 玄関の段差でつまづきそうになった経験はありませんか
- 立ち上がる際に手すりを欲しいと思ったことはありませんか
- 冬でも暖かい浴室にしたいと思いませんか
さらにチラシは手元に保存できるメリットもあります。
手元に保存しておくと、簡単に読み返せるため配布から時間が経っても集客効果が見込めます。
チラシのデメリット
チラシのデメリットとしては、扱える情報に限りがあることです。
チラシは紙面に情報を記載するため、どんなに頑張っても情報を詰め込めるのは紙1枚分のみです。
そのため、記載する情報を厳選しないと、結局何が言いたいのかわからないチラシになる恐れがあります。
またチラシは配布エリアにしか情報が届けられません。
一方でネットは、エリア・年齢関係なく不特定多数にリーチ可能です。
さらにチラシは制作・配布に手間と費用がかかります。
作成後は、各家庭に配布しなければならないためWeb広告より費用がかかることもあります。
チラシ作成3つのポイント
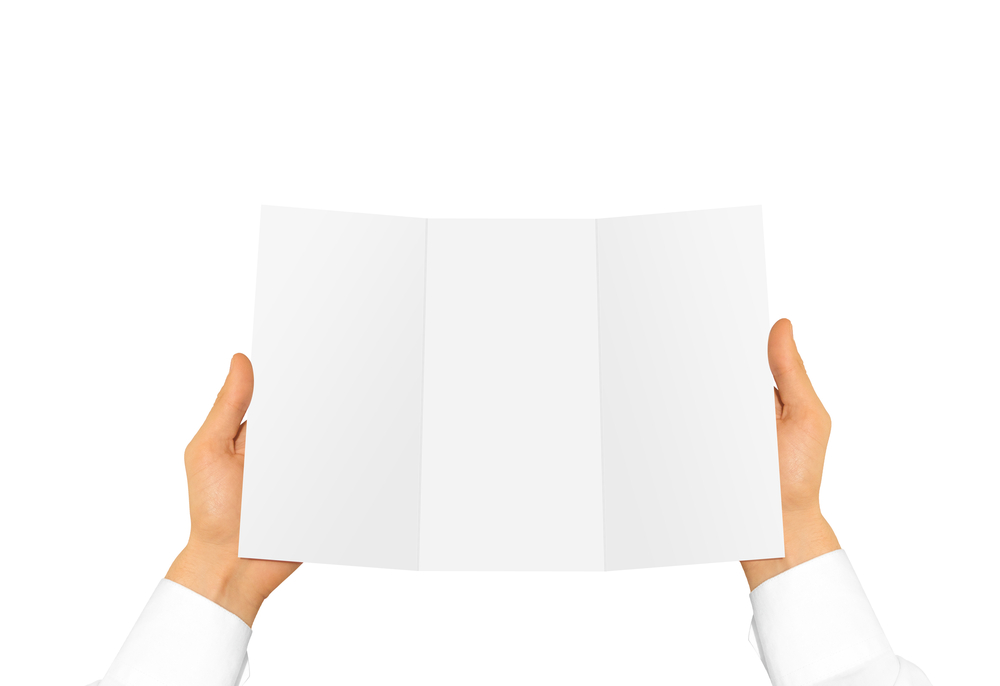
ここでは、チラシの作り方として、目的とターゲットを決定する重要性と、用意する必要があるものやデザイン制作について説明します。
目的とターゲットの決定
チラシを作る場合、まずは目的とターゲットを明確にしましょう。
ターゲットや目的を明確にすると、集客効果の高いチラシが作成できます。
ターゲットや目的を定めるときに便利な考え方が「5W1H」です。
5W1Hは、以下の単語の頭文字のことです。
- Who(だれが)
- When(いつ)
- Where(どこで)
- What(なにを)
- Why(なぜ)
- How(どのように)
5W1Hに情報を当てはめることで、ターゲットや目的を絞れます。
工務店では、以下のようなイメージで活用しましょう。
- Who(新婚の夫婦が)
- When(結婚を機に)
- Where(郊外で)
- What(戸建てを)
- Why(子供ができたときを想定して)
- How(比較検討する)
5W1Hの活用で、ターゲットと目標を絞れるため、特定の方に刺さる魅力的なチラシの作成ができます。
用意するもの
チラシ作成の際は、下記を用意しましょう。
- チラシの構成
- 伝えたいメッセージ
- おおまかな文章
- 画像(写真・イラスト)
- ラフレイアウト
上記を用意しておくと作成がスムーズにおこなえます。
また、ラフレイアウトの用意もおすすめです。
実際のチラシのサイズを想定したレイアウトがあれば、文字の大きさやレイアウト、バランスなどもチェックできます。
画像に関しては自社でオリジナルの写真を撮影したり、イラストを作成したりするほか、素材集から購入することも可能です。
工務店の規模が小さく予算に余裕がないといった場合は、スマートフォンで撮影した画像を使用しましょう。
デザイン制作
用意したものをもとにチラシを作成します。
注意点は、ラフレイアウトをそのままチラシにしないことです。
ラフレイアウトをそのまま使用すると、パッとしない印象になります。
ターゲットの目を引くためには、下記のソフトを使用して装飾を加えましょう。
- PowerPoint(パワーポイント)
- Word(ワード)
- Adobe Illustrator(イラストレーター)
- Adobe InDesign(インデザイン)
最もおすすめのソフトはPowerPointです。
PowerPointは、無料テンプレートが豊富でデザイン経験がない方でも、簡単にチラシの作成が可能です。
無料テンプレートは、下記のリンクから入手できます。
簡単にチラシを作成する方法

簡単にチラシを作成する方法は、下記の2つです。
無料のテンプレートを活用する
最もおすすめの方法は、無料テンプレートの活用です。
無料テンプレートは、指定された箇所の文字や画像を変更するだけで、誰でも簡単にチラシの作成ができます。
エニワン株式会社が提供している無料テンプレートを例に説明します。

上記①〜④の文章・画像・イラストを変更するだけで、自社オリジナルのチラシが簡単に作成できます。
パソコンとPowerPointがあれば、簡単に編集が可能です。
無料テンプレートを使用したい方は、下記のリンクよりお問い合わせください。
チラシ制作会社に依頼する
「チラシ作成に人員を割けない」と考える方は、チラシ作成会社に依頼しましょう。
チラシ制作会社のメリットは、完成度の高いチラシが作成できることです。
ただしプロに依頼するとしても丸投げでは、集客に効果のあるチラシはできません。
制作会社に依頼する場合も、先述した5W1Hは決めておきましょう。
また制作会社への依頼は、費用がかかります。
そのため依頼する際は、費用対効果に見合うのかを事前に検証しましょう。
【工務店】チラシ作成する際のデザイン5つのポイント

工務店がチラシを作成する際に気を付けるべきポイントを5つ解説します。
問い合わせや見学会に誘導する
チラシでは、問い合わせや見学会に誘導しましょう。
家は高額で、チラシを見ただけで購入を決断できる方はほとんどいません。
そのため、問い合わせや見学会に誘導し、自社で家を建てる魅了を説明できる機会を設けるのがおすすめです。
家を建てるメリットを記載する
家を建てるメリットを記載しましょう。
- 家賃を支払う必要がなくなる
- ペットを飼える
- 子供の足音を気にする必要がない
- バリアフリーの住宅に住める
ターゲットに合わせて、記載するメリットを変えましょう。
子育て世帯がターゲットならば「子供に関するメリット」、高齢者が対象なら「バリアフリーなど住みやすい住宅」というイメージです。
次のアクションを明記する
チラシを読んだ方に、次におこなってほしいアクションを記載しましょう。
- チラシ内容の問い合わせ
- 見学会の予約
- LINEへの登録
上記のようなアクションが記載されていないと、チラシを読んだ方は何をすべきかわかりません。
そのため、次のアクションへとつながらず、チラシを作成する効果が出ません。
チラシを作成する際は、チラシを読んだ方に「次は何をしてほしいのか」記載しましょう。
複数の価格を記載しない
価格を記載する場合は、複数の価格を記載しないようにしましょう。
いくつも価格が記載されていると、ターゲットはどれが本当の価格か判断できません。
特に「地域最安値」といった価格に強みのある工務店・リフォーム会社は、注意が必要です。
チラシの効果を計測できるようにする
チラシの効果を測定できるデザインにしましょう。
Webの集客方法と異なり、チラシでの集客は工夫をしないと集客効果の計測ができません。
集客効果の計測ができないと、チラシの改善やチラシそのものに効果があるかが判断できないため、必ず効果が計測できるような工夫が必要です。
例えば1枚ずつ番号を割り振り、問い合わせや見学会参加時にチラシを持ってきた方に粗品をプレゼントする方法があります。
番号を確認すれば、どの地域で反響があったのか確認できるようになります。
まとめ
本記事では、工務店がチラシを作るときのメリットとデメリット、チラシの作り方や集客のためのポイントについて解説しました。
チラシは、高齢者をはじめとしたネットで情報収集しない方に有効な集客方法です。
チラシの活用で、ネット集客とは異なる層に情報を届けられます。
ただし「チラシの作成はデザインセンスがないと難しいため、自社では作れない」と考える方もいるでしょう。
上記のように考える方は、エニワンの無料テンプレートの活用がおすすめです。
指定の箇所の文言や画像・イラストを変更するだけで、誰でも簡単にチラシの作成ができます。
気になる方は、下記のリンクよりお問い合わせください。