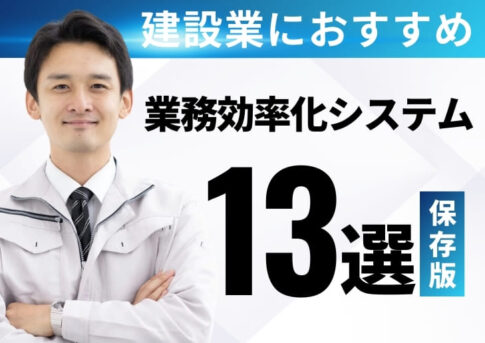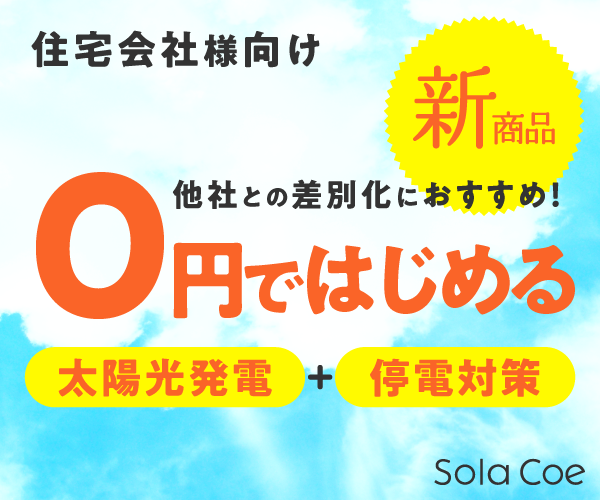近年は材料の仕入れ価格や人手不足による人件費の増加により、建設コストの上昇に悩んでいる工務店経営者は多いのではないでしょうか。
仕入れ価格や人件費は、1社だけの対策でどうにかできるものではありません。
ただ建設コストが上昇している要因は他にもあるため、そちらの原因であればすぐに対策が可能です。
この記事では建設コストが上昇する要因や、建設コストを削減する方法について解説します。
目次
建設コストを左右する要因

はじめに建設コストを左右する以下4つの費用について解説します。
材料費
材料費とは文字通り、建物を建てるために使われる木材や鋼材の仕入れにかかる費用です。
材料費は「直接材料費」と「間接材料費」に分類されます。
- 直接材料費:特定の工事にだけ使用する材料
- 間接材料費:複数の工事で使用する材料
間接材料費はその工事に使用した分だけを工事原価に組み入れます。
労務費
労務費とは工事に関わった方の賃金や給料、福利厚生費を指します。
現場監督や作業員など従業員が、特定の現場に関わった場合の費用を労務費として計上します。
雇用形態は問わず、パートやアルバイトであっても特定の工事に従事し、発生した費用は労務費としては使われることには注意が必要です。
なお工事と関わらない総務部や経理部などの管理部門の従業員の給料は、販売管理費や一般管理費に分類されます。
外注費
建設業は外注の割合が多いため、労務費とは別に協力業者に支払った費用を外注費として計上します。
- 自社で材料を手配し、工事を協力業者に依頼したケース
- 外注の施工管理者を手配したケース
上記のような場合は外注費として計上します。
経費
経費とは、材料費・労務費・回収機に該当しない費用のことです
たとえば現場事務所の光熱費や通信交通費などが該当します。
いわゆる工事を円滑・快適に進めるための費用と理解すれば良いでしょう。
工事費には「直接工事費」と「間接工事費」があり、経費は後者に当たります。
建設コストが上昇する原因

建設コストが上昇する原因を以下3つ解説します。
工事ごとにコストが上昇する要因はさまざまです。
この記事で解説する原因をしっかりと理解し、建設コストの上昇を防ぐための対策を考えましょう。
工事の遅延
工事が遅延し、工程表通りに工事が進められないとコストが上昇します。
たとえば工事が遅延し竣工時期が後ろになった場合、重機や発電機などリース品の利用日数が伸びてしまい、余計にリース料がかかってしまいます。
また工事が遅延しても竣工時期が変わらなければ、予定よりも多くの職人さんを手配しなければならなくなり、想定より人工代がかかってしまいます。
上記の理由により人的ミスや天候などにより、工事が遅延してしまうと建設コストが上昇してしまいます。
発注ミス
発注ミスも建設コストが上昇してしまう要因です。
- 想定の数よりも多くまたは少なく発注してしまった
- 必要でない材料を発注してしまった
- 発注した材料が必要な日に届かなかった
- そもそも発注していなかった
発注ミスがあると再度発注する手間がかかる、職人の手持ち時間が発生してしまい、予定通り工事が終わらなくなってしまうなどの理由から建設コストが上昇します。
特に必要な材料が必要な日に届いていないと、工事が進められないため、工事の遅延にもつながりさらに建設コストが上昇する原因となる可能性が高いです。
積算ミス
積算ミスも建設コストが上昇する原因の一つです。
たとえば部材の拾い漏れが該当します。
積算ミスがあると、見積書に必要な項目を載せられないため、見積り価格が低く算出されてしまうことになるでしょう。
本来必要だった項目が抜けている状態で受注してしまうと、想定していた建設コストが実際は上昇します。
建設コストを削減する方法

建設コストを削減する以下3つの方法を解説します。
最適な方法は個々の会社によって異なります。
この記事を参考に自社に最適なコスト削減方法を選んでください。
仕入れルートの最適化
仕入れルートの見直しをおこないましょう。
仕入れ業者の中には、受けた仕事をそのまま下請け業者に依頼するブローカーのような存在がいます。
ブローカーは利益を数%上乗せするだけで、工事や材料で手配など下請け業者に丸投げしています。
仕入れルートの中にブローカーがいると、仕入れ金額が高くなってしまい工務店側には何もメリットがありません。
仕入れからブローカーを除くだけで、数%の建設コストの削減ができます。
加えて最近は建設業界を上げて、多重下請け構造を改善しようとする流れができています。
下請け構造が複雑になると、元請け業者の管理が行き届かない、下請け業者に適切な報酬が支払われないと言った問題があるためです。
建設コスト削減と建設業界の流れ、どちらの観点からも仕入れルートの最適化は実施するべきです。
余裕のある工期設定
余裕のある工期設定も建設コスト削減には重要です。
工事が遅延すると、建設コストが上昇しやすくということは先述の通りです。
そのため多少工事が遅延しても問題が発生しないように工期設定をしていれば、建設コストが上昇しにくくなります。
最近は2024年の時間外労働の上限規制、4週8休の浸透を目標に業界を挙げて、余裕のある工期の設定を目指しています。
すでに受注してしまった工事は難しいでしょうが、これから受注する工事であれば、工期の交渉はおこないやすいです。
はじめの内は工期の交渉に足踏みしてしまうかもしれませんが、勇気を持ってチャレンジしてみてください。
業務効率化システムの導入
業務効率化システムを導入することで、建設コストの削減がおこなえます。
特に工務店業務に特化している業務効率化システムは、見積書の作成から実行予算の作成や原価管理までを一気通貫でおこなえることがメリットです。
つまり1つのシステムを確認するだけでお金の流れがわかるため、建設コストが上昇したのかを一目で把握できます。
また業務効率化システムの活用により、会社全体の業務の生産性を上げることが可能です。
特に施工管理者はまだまだアナログな手法で業務を進めており、残業ありきでないと仕事が終わらないという会社が多いです。
業務効率化システムを導入すれば、デジタルやITの力で効率的に業務が進められるようになります。
原価管理を例に説明します。
導入するシステムによっては作成した見積書の情報を実行予算に流用が可能です。
データの流用することで、同じ情報を入力する必要がなく、入力の際の人的ミスも抑制できます。
わざわざ同じ情報を手打ちする時間が減るため、施工管理者が本来おこなうべき図面のチェックや納まりの検討などに時間を使えるようになります。
また誰が発注したのか、発注金額はいくらなのか、想定していた件かと発注金額の差異はいくらなのかを瞬時に判断できます。
そのため建設コストが上昇した要因をすぐに分析可能です。
業務効率化システム導入によっては業務の生産性を向上させ、建設コストの上昇を防ぎます。
業務効率化システムが気になる方は、おすすめのシステムを10社比較している記事をご確認ください。
まとめ
この記事では建設コストが上昇する要因や、建設コストを削減する方法について解説しました。建設コストは、工事の遅延や発注ミス、積算ミスで上昇するケースが多いです。
また建設コストを削減する方法は以下の3つです。
- 仕入れルートの最適化
- 余裕のある工期設定
- 業務効率化システムの導入
上記3つの中で最もおすすめするのは、業務効率化システムの導入です。
ただ「業務効率化システムを導入したいと思っても、どれを選んだらいいかわからない」と悩んでしまう方もいるでしょう。