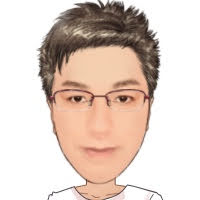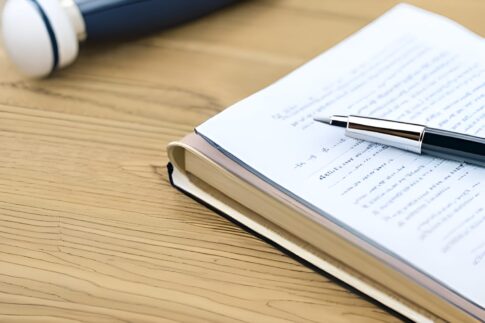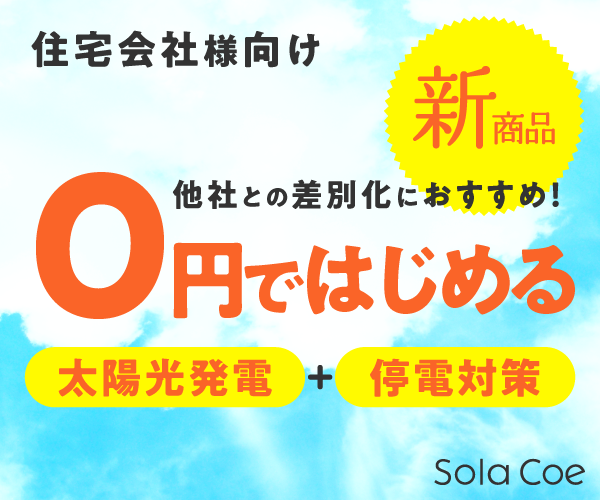建物修繕や改修をおこなうには、屋根工事が必要です。
屋根工事は建設業のひとつであり、専門工事に分類される作業となっています。
屋根工事を事業として新たに展開する場合、どのような工事内容なのか理解しておくことが大切です。
当記事では、屋根工事の詳細から工事内容の種類・具体的な手順まで詳しく解説します。
屋根工事について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
屋根工事とは

屋根工事とは、屋根の構造体や屋根材を葺く工事、屋根に関連する板金工事などを指します。
それでは屋根工事の必要性や屋根の寿命について詳しく説明します。
屋根工事の必要性
屋根工事は、雨漏りや強風、地震などの被害、住宅の資産価値を守るために必要です。
屋根にはさまざまな負担がかかっているため、徐々にダメージが蓄積されていきます。
また、地震が多い日本では、瓦のズレや、釘の緩みなどが生じやすいため、メンテナンスが不可欠です。
もしも屋根をメンテナンスしなければ、雨漏りで室内に雨が流れ込んだり屋根材が広範囲にめくれあがったりと被害にあう可能性も高いです。
重大な問題が発生する前に屋根工事をおこなうことで、屋根の被害を最小限におさえられます。
屋根の寿命について
屋根の寿命は、使用する屋根材の種類によって耐用年数が大きく異なります。
例えば日本の代表的な和瓦は、適切なメンテナンスをおこなうことで50年以上の使用が可能です。
また、スレート屋根は20年~30年程度、ガルバリウム鋼板は30年~40年が一般的な寿命となります。
屋根材の寿命を延ばすためには、定期的なメンテナンスが必要です。
瓦屋根は漆喰の補修を15年程度でおこない、スレートやガルバリウム鋼板は5年〜10年ごとの塗装が推奨されています。
また、建物の立地環境も屋根の寿命に大きな影響を与えています。
積雪地帯では融雪剤による劣化が起こりやすく、海に近い地域では塩害の影響が大きいです。
このような立地の場合は早めに適切な点検と補修をおこなうことで、屋根の寿命を大幅に伸ばせるでしょう。
屋根工事の種類

屋根工事には、以下のような工事の種類があります。
詳細や特徴を説明するため、ぜひチェックしてください。
葺き替え工事
葺き替え工事は、既存の屋根材を全て取り除いて新しい屋根材を取り付ける屋根の工事です。
全て交換する「全面葺き替え工事」と「部分葺き替え工事」の2種類があり、下地の交換・補修をおこなったあと、新しい屋根材を葺いて終了となります。
耐震性や防水性が向上し、屋根の寿命が延びる点がメリットです。
ただし、屋根が一時的に取り払われるため、雨漏りのリスクがある点にデメリットがあります。
30坪ほどの戸建住宅であれば、150万円~200万円の費用が目安となっています。
屋根工事のなかでは最も大規模なものとなり、屋根に生じている根本的な問題を解決できる工事です。
葺き直し工事
葺き直し工事は、既存の屋根材を再利用する屋根の工事です。
防水シートや野地板など屋根の下地を修復し、防水シートの劣化や穴あきに対応できます。
既存の屋根材を再利用するため、屋根材自体の寿命が長い陶器瓦でおこなわれるケースが多いです。
葺き直し工事をおこなうことで、耐震性や防水性が向上して屋根の寿命が延びます。
ただし、葺き替え工事と同様に屋根が一時的に取り払われるので、雨漏りのリスクがある点にデメリットがあります。
こちらも葺き替え工事と同じく、150万円~200万円の費用が目安です。
ただし、再利用する既存の屋根材自体が劣化している場合、葺き直し工事ができない場合がある点に注意しましょう。
屋根カバー工法
屋根カバー工法は、既存の屋根の上に新しい屋根を重ねる工事です。
「重ね葺き」や「カバールーフ工法」とも呼ばれており、既存の屋根を撤去しないことから材料費や工費などのコストを節約できます。
さらに工期が短く屋根も二重になるため、断熱性や遮音性を高められる点がメリットです。
ただし、屋根の重さが2倍になるため、施工前には耐震性のチェックが欠かせません。
塗装工事
塗装工事は屋根の表面を再塗装する工事です。
屋根だけでなく、建物の外壁や内壁、床などの塗装も工事範囲として含まれています。
塗装工事には高圧洗浄や下地補修、下塗り、上塗りなどの工程があります。
屋根の見た目を回復でき、新しく塗り替えればイメージを変えることも可能です。
新築から10年が経過したり、塗膜の劣化が著しかったりするときが塗装工事のタイミングとなります。
また、紫外線や雨風などから建物を守ることもできるため、資産価値を維持する目的で施行されることも多いです。
費用は塗料代や工事費、足場代などによって大きく変動します。
屋根材の修繕工事
屋根材の修繕工事は、屋根の劣化部分だけを補修する工事です。
屋根の傷んだ部分のみを修繕することで、屋根や家本体の寿命を延ばせます。
瓦屋根の場合、割れた瓦を接着剤で接着したり瓦を差し替えたりします。
破損の度に修繕を依頼するのが億劫な場合、リフォームで全面改修すること多いです。
屋根の傷んだ部分を早い時点で補修すれば、被害箇所が広がってしまうことや屋根内部に影響が及ぶことを防止できます。
傷んでしまった屋根の修理を依頼する場合、工事の規模によって数万円〜200万円が相場となります。
漆喰補修/交換工事
漆喰補修/交換工事は、瓦の接着用粘土である漆喰の塗り直す工事です。
漆喰補修の場合、見た目の美しさと耐久性を追求することを目的とします。
状況によっては残っている漆喰の上から新しい漆喰を重ねて塗ることもありますが、1から塗り直しするケースが多いです。
既存の漆喰をそのままにしながら上から漆喰を塗る「詰め増し」という方法もありますが、施工後の寿命が短いのであまりおすすめしていません。
古くなった漆喰を剥がし、新しいものに塗り替えていきます。
瓦の使われる漆喰は年月の経過によって傷むため、定期的に塗り替えが必要です。
棟板金交換工事
棟板金交換工事は、屋根の頂点にある棟板金を新しいものに交換する工事です。
棟板金は屋根の他の部分と比べて傷みやすいため、部分的に交換するケースが多いです。
棟板金は屋根板と屋根板の間を保護する役割があり、雨水の侵入を防ぐために定期的な点検や交換が必要となります。
スレート屋根や金属屋根が金交換工事の対象です。
雨樋修理/交換工事
雨樋修理/交換工事は、雨樋の修理・交換をおこなう工事です。
雨樋の詰まり解消や壊れた雨樋を交換することで、建物の雨漏りを防ぎます。
雨樋が壊れたままになっていると、雨水が屋内へと侵入して建物の寿命に悪影響を及ぼします。
経年劣化や強風、自然災害などによって破損することが多いため、定期的なメンテナンスが必要です。
防水工事
防水工事は、屋根やバルコニーの防水材を改修する工事です。
雨にさらされる場所を水から守ることで、建物の耐久性を保ちます。
防水工事の工法には、アスファルト防水やシート防水、塗膜防水、 浸透性防水などがあります。
防水材のメンテナンスを怠ると雨漏りの原因となるため、メンテナンスの優先順位が高い工事です。
天窓工事
天窓工事は、屋根や天井に窓を設置する工事です。
「トップライト」や「スカイライト」、「ルーフ窓」とも呼ばれており、窓を設置することで建物内の日当たりが良くなります。
ただし、雨漏りや結露が発生するリスクがあるため、定期的な掃除やメンテナンスが必要です。
採光のみに使う開閉できない「固定式」や換気に役立つ「開閉式」などがあり、建物に合わせて選択できます。
屋根工事で重要なポイント

屋根工事をおこなう際には、以下のようなポイントが重要です。
足場の設置
屋根工事では、基本的に足場の設置が必要です。
屋根工事は高所の作業となるため、足場を設置しながら安心に進めなくてはいけません。
特に傾きが30度以上ある場合、危険性が高いため足場の設置は必須です。
足場があれば職人による作業の安全性を高め、施工品質を確保できます。
そのため屋根工事をおこなう際には、必ず足場を設置しましょう。
雨が降った場合における対応
屋根工事中に雨が降った場合、工事は中断しなければなりません。
屋根工事で使用する木材などが濡れてしまうと、工事が失敗する原因となります。
工事中に雨が降ったなら、ブルーシートなどで建物を覆いながら対策が必要です。
天気予報をチェックし、工事日に雨が降りそうであれば別日に変更することも検討しましょう。
屋根工事の流れ

屋根工事の基本的な流れは、以下の通りです。
1.施主との打ち合わせ
はじめに、施主との打ち合わせから屋根工事の方向性について話し合います。
屋根の雨漏りや経年劣化など施主によって悩みは異なるため、打ち合わせを通じて解決策を見つけていきます。
施主によっては要望がいくつもあるため、打ち合わせから1つずつ整理することが大切です。
対面での打ち合わせが難しい施主には、ZoomなどのWeb会議ツールを使った方法も提案すると良いでしょう。
2.作業工程の提案
打ち合わせから方向性を明確化できれば、屋根工事の作業工程を提案します。
何をどのようにいつまで対応するのかを伝えることで、施主に内容を理解してもらいながら進めることが可能です。
屋根工事にはいくつもの方法があるため、どのような作業をおこなうのかによって必要とする期間が異なります。
屋根工事をスムーズに進めるためにも、適切な作業工程を提案するようにしましょう。
3.見積もりの提示・契約
作業工程を提案し、施主から承諾を得られたら、見積もりを提示します。
屋根工事に必要となる材料費や人件費などを見積書にまとめ、施主に全体的な費用をチェックしてもらいます。
追加費用が発生する恐れがある場合、見積書の備考欄に記載することで契約後のトラブルを防止可能です。
施主に見積もりをチェックしてもらい、承諾を得れば契約締結となります。
4.工事開始
契約締結後、指定日から屋根工事を開始します。
工事前には施主へ工程表を送ることで、現在の進捗状況について把握してもらいます。
屋根工事にかかる期間は工事内容や規模、天候などによって異なりますが、葺き替え工事であれば1週間~10日程度が目安です。
雨天の際には、2週間ほどかかる場合もあります。
工事途中に施主から調整や変更の要望がある場合、状況に応じて柔軟な対応をおこないましょう。
5.引渡し・アフターサービス
工事終了後、施主に一度チェックしてもらい問題がなければ引渡しとなります。
一般的にはアフターサービスを設けており、一定期間内は施主からの悩み相談や追加作業などをおこないます。
以上が屋根工事の基本的な流れです。
屋根工事業者に必要な資格・許可

こちらでは、屋根工事業者に必要な資格や許可についてご紹介します。
優良業者であることを施主にアピールするためにも、取得を検討しましょう。
建築施工管理技士
建築施工管理技士は、建築物の施工において品質や安全、工程、コストなどの管理をおこなう国家資格保有者です。
建築現場の運営を支える中核的な存在として、建築物の質向上を図る役割があります。
屋根工事が3,500万円以上になる場合、建築施工管理技士の資格が必要です。
大規模な屋根工事の依頼を受注する際には、建築施工管理技士の資格を取得している現場監督を用意しましょう。
外装劣化診断士
外装劣化診断士は、建物の外装の劣化状況を診断して修繕やメンテナンスを提案できる資格です。
外壁や屋根の劣化度合いを的確に把握し、建物の寿命を延ばす役割があります。
診断結果に基づき、建物の維持管理に適切な指示を提示できます。
屋根工事の診断から適切な提案をおこなうためにも、外装劣化診断士の資格取得も検討しましょう。
建設業許可
建設業許可は、建設業を営む事業者が取得する許可です。
建設業法に基づいて定められており、取得することで建設業許可番号が発行されて建設業に関するさまざまなルールに従いながら建設工事を請け負うことができます。
建設業許可を取得していない場合は、1件あたり500万円(税込)未満の軽微な工事しか請け負えません。
複数の業者が工事に関わる場合は「一式工事」として扱われるため、上限が1,500万円になるケースもあります。
建設業許可の申請には、建設業許可申請書や工事経歴書、使用人数、誓約書などさまざまな書類が必要です。
詳しくは国土交通省または都道府県の建設業担当窓口で、正しい申請手順を理解しておきましょう。
道路使用許可
道路使用許可は、道路の本来の用途とは異なる使用行為をおこなう際に警察署長の許可を得る制度です。
足場や工事車両の関係で道路を使用する場合、道路使用許可を取る必要があります。
一時的に道路をふさぐ場合は「道路使用許可」、足場が道路にはみ出す場合は「道路占用許可」の取得が必要です。
どちらも警察署で申請書類を提出する必要があり、申請手数料が別途かかります。
無断で道路を使用することは違法となるため、屋根工事で道路を使用する際には必ず道路使用許可を取るようにしましょう。
まとめ
今回は、屋根工事の詳細から工事内容の種類・具体的な手順まで詳しく解説しました。
屋根工事は雨漏りや強風、地震などの被害、住宅の資産価値を守る役割があります。
この工事を定期的におこなうことで雨漏り防止やイメージの変更、耐久性の強化ができます。
屋根材の種類や劣化症状によって工事方法が異なるため、診断をしながら施主に工事方法を提案する必要があります。
ぜひ当記事でご紹介した屋根工事の方法を参考にしながら、自社の作業範囲を広げてください。
建築現場博士がおすすめする工務店・建築業界の業務効率化ソフトはAnyONEです。
導入実績2,700社超の業界No.1基幹システムで、国交省「第一回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択されています。
エクセルのような操作感で、レイアウトもマウスで変更できるため、ITが苦手な方でも簡単にお使いいただけます。
また、システムの導入後も徹底的なサポートを受けられるため、安心して運用できるでしょう。
大手・中堅企業様から一人親方様まで規模感を問わず、業務状況に合わせて様々な場面でご利用いただけます。