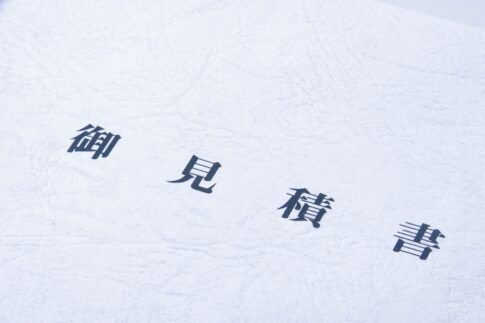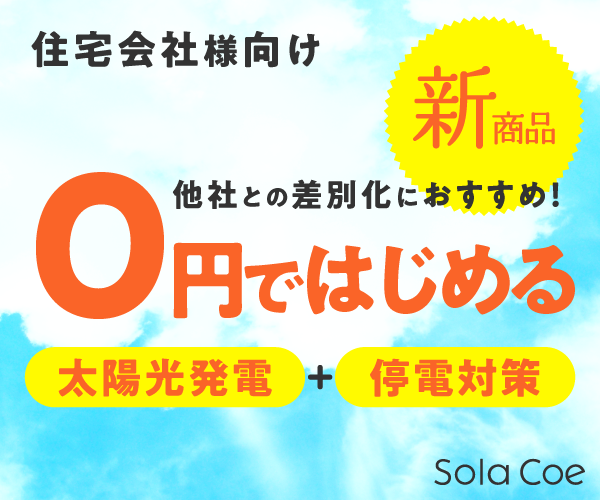建設業を営むにおいて、工事現場ごとに請負業務の内容や売上、原価、利益、工期などを管理することは非常に重要なことです。
その管理の方法として存在するのが『工事台帳』と言われる管理帳票です。
本項では、工事台帳に記載すべき内容や作成の目的、簡単な工事台帳の作成方法を解説いたします。
目次
工事台帳とは?

工事台帳とは、工事現場ごとの受注内容・売上と原価、利益、工期などを一元的に管理する台帳のことをいいます。
とりわけ、日々工事現場に要した費用を確認することは適正な利益率の確保に欠かせません。
完成後にとりまとめると目標としていた利益率を下回り、赤字になっていたことが発覚してもあとの祭りです。
そのため、工事台帳へ工事に要した費用や工事の進捗を記載し、日々確認を行うことは非常に重要なことであると言えます。
工事台帳へ記載する費用は以下の項目です。
材料費
材料費とは、建築現場で必要な資材などの仕入れに要した費用です。
資材の原価のみならず、工事現場へ資材を搬入するための運搬費用なども材料費に含まれます。
労務費
労務費とは、工事に関わる人員の人件費を指します。
後述する外注費と混同しがちですが、労務費に該当する人件費とは、以下3つの条件を満たした費用に限られます。
- 自社で雇用している社員のうち
- 建築現場で勤務している人の
- 給料や手当
外注費
外注費とは、建築現場で勤務している方のうち、下請けや派遣など外部に委託している作業員に対して支払う報酬や委託料を指します。
経費
先述したの材料費・労務費・外注費に含まれない建築現場で要した経費です。
建築現場で要した費用には、重機設備等のレンタル費用や上水の利用料などのほか、現場事務員の給与や手当なども含まれます。
工事台帳の義務

建設業法ではさまざまな書類に保存期間が求められています。
書類の保存期間が定められている理由は、建物は数十年間にわたる使用が前提となっており、万が一トラブルや事故が発生した場合、スムーズな原因解明を可能とするためです。
工事台帳の作成や保存について、建築業法ではどのように定められているのでしょうか。
作成の義務
建設業法ではさまざまな書類作成義務が定められています。
しかし工事台帳は建設業法上の作成義務がある書類ではないため、工事台帳を法的観点から作成する必要性はありません。
ただし、上述の通り工事ごとの原価や利益を確認することは、経営の健全性をリアルタイムで確認することと同義と言えるため、工事台帳の作成は積極的におこないましょう。
保存の義務
建設業法では工事台帳の作成義務がありませんため、当然保存期間の定めもありません。
しかし、建設業法では以下のような書類に保存期間が設けられています。
- 帳簿および不随する書類
帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載することが必要であるほか、契約書などを添付することが必要です。
- 営業に関する書類(発注者から直接建設工事を請け負った場合に限られます)
営業に関する書類には、完成図・打ち合わせ記録・施工体制図などが挙げられます。
建設業法上は工事台帳に作成と保存の義務はありませんが、せっかく作成した工事台帳を保存しないことはおすすめできません。
関連する書類に保存期間が求められている理由は、有事の際の原因究明以外にもさまざまな理由が考えられます。
業者間での金銭トラブルや工事完了後に発生した労災事故検証など、色々なシーンで当時の工事状況を振り返ることは容易に想定されます。
関連する書類に保存期間が求められている以上、工事台帳もセットで保存しておくことで、後日当時の状況を確認するシーンで工事台帳が役立つことは明白です。
工事台帳を作成するメリット

工事台帳を作成する具体的な実務面でのメリットについて説明します。
現場ごとの収支把握
安定した利益を確保し企業経営を健全なものにするためには、工事台帳を作成し現場ごとの収支を把握することが必要です。
また、工事台帳を現場ごとに作成することで、自社の積算能力の向上も期待できます。
自社の積算能力の向上は適切で的確な見積提示と同義であり、過度な価格競争に晒されるリスクを回避することにも繋がります。
総じて、経営基盤の安定が図れることがメリットです。
公共工事への参加
建築業者が国や地方公共団体が発注者となる工事を請け負うときは、経営事項審査という審査を受けなければなりません。
【参考】経営事項審査及び総合評定値の請求について-国土交通省
入札に参加しようとする建築業者が欠格事由に該当していないかどうかを判断したうえで、客観的事項と主観的事項の2点を点数化する形でおこなわれます。
このときおこなわれる「客観的事項」のことを「経営事項審査」と言います。
一連の審査の中で決算報告書などを提出しますが、合わせて提出が必要な書類の中に「工事台帳」が含まれています。
工事台帳がないと工事に要した費用の内訳が性格に把握できません。
つまり経営事項審査を通過することはできないため、公共事業の受注ができないということです。
受注販路拡充のためにも、工事台帳の作成は必須と言えるでしょう。
税務調査への対応
建築業界は、会計基準が定められているものの会社独自のローカルルールに基づいて仕訳がなされていることが多く、税務調査の対象になりやすい業界とです。
国税庁が発表した令和2年度の法人税等の調査実績の概要では、不正発見割合の多い業種として、一般土木建築工事が6位に、職別土木建築工事が7位に、土木工事が10位にランクインしています。
国税庁が現地調査により確認を行う事項として売上や費用の計上タイミングが考えられます。
税務調査に対応する際に工事台帳が作成しておくことで、原価計算や工事進捗が一目瞭然となるため、対応がスムーズです。
さらに、建築業法で定められている各種帳票との整合性を普段から確認しておくことで、不正を疑われることもなくなります。
簡単な工事台帳の作り方
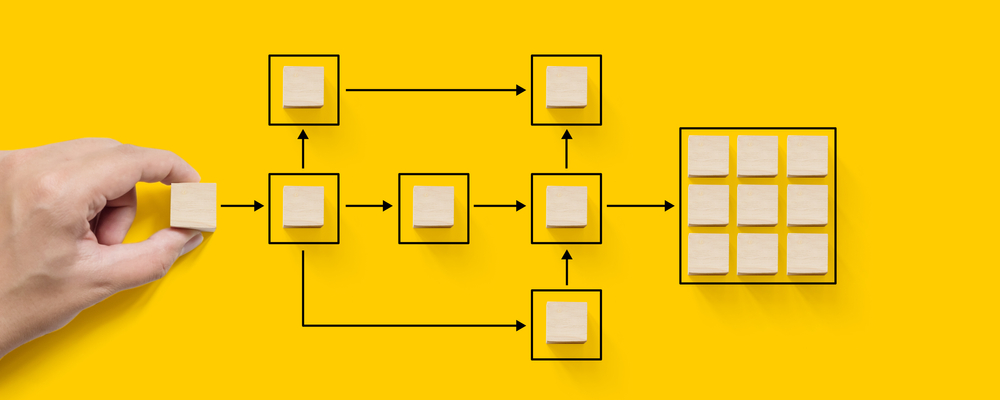
工事台帳がまだ社内にない会社ではどのように工事台帳の作成に取り掛かればよいのでしょうか。
以下3つの方法があるため、会社の状況や規模に合わせて選択してください。
工事管理システム
工事台帳をフォーマットから作成することは非常に手間がかかります。
そこで、規模が大きい工事を受注している会社や、規模が小さくとも多くの工事を受注している会社にはシステムを導入するのがおすすめです。
最近のシステムはシンプルで使い勝手も良く、感覚的に操作ができるものが多いため、ITアレルギーのある会社であっても親和性が高いと言えます。
同時ログインが可能で、複数人と同時に作業がおこなえます。
また操作が簡単なシステムが多く、ITが苦手な方でも操作方法につまずくことは少ないです。
有料なシステムはサポートがしっかりしており、運用中にトラブルが発生してもすぐに解決できます。
工事管理システムは便利ですが、機能が充実しているシステムは導入コストや利用コストがかかることが多いです。
コストが気になって導入をためらう方は、IT導入補助金の活用を検討してください。
IT導入補助金を活用すると、導入にかかる費用の一部が補助されるため、資金に余裕のない会社でもシステムを導入できます。
気になる方は、下記のリンクより無料でプレゼントしている「IT導入補助金 申請まるわかりBOOK」をダウンロードしてください。
またシステムの利用方法や操作方法に社員ごとに、理解度の差が生まれてしまうこともデメリットです。
しかしシステム提供会社によっては、導入時の説明会など手厚いサポートをおこなってくれるため、業務に支障が出ることは少ないでしょう
エクセル
さまざまなシチュエーションで利用されるエクセルも工事台帳として使用することが可能です。
表計算ソフトとして簡単に導入できます。
またインターネット上にある無料のテンプレートを使うことで、すぐにでも工事台帳の利用が可能です。
エクセルは表計算ソフトとして有用で、テンプレートさえ作成できれば工事台帳としても十分に活用ができます。
ただし、エクセルは原則1人しか操作・閲覧ができません。
リアルタイムでの進捗確認が困難で、社員の方々のエクセルスキルによって活用度合いに差が出る傾向があります。
また、エクセルで作成したフォーマットのメンテナンスには関数やマクロなどの知識が不可欠です。
フォーマット作成者が退職したときに、メンテナンスや改変が困難になるリスクがあり、運用が属人化しやすいという点には気をつけましょう。
Googleスプレッドシート
最近はエクセルではなく、スプレッドシートを利用する機会も増えてきました。
エクセルに似た仕様ですが、スプレッドシート独自のポイントもチェックしましょう。
Googleスプレッドシートは、複数人が同時に閲覧・編集ができるインターネット上のエクセルのようなツールです。
エクセルと操作性も似ているため、初めて使う方にも使いやすいツールと言えます。
一方、インターネット上のスプレッドシートにアクセスする形となるため、情報漏洩リスクという真逆の側面も存在しています。
リモートワークなど外部から接続される方が多い環境では注意が必要です。
Googleスプレッドシートに詳しく知りたい方は、Googleスプレッドシートで工程管理をおこなう方法について解説した記事をご確認ください。
まとめ
工事台帳は建築業を営むにあたり非常に重要な帳票の一つです。
有効に活用することで経営の健全化が図れるほか、積算の精度も向上し、業務の受注幅が広がります。
エクセルやスプレッドシートで作成することが多い工事台帳ですが、現在は安価でさまざまなシステムも多数存在しているため、一度検討されてみてはいかがでしょうか。