人材不足や資材の高騰による経営難を解決するためには、補助金や助成金の利用が必要不可欠です。
しかし、建築会社の経営者は「どのような補助金・助成金が利用できるのかわからない」という悩みもあるでしょう。
当記事では、建設業で利用できるおすすめの補助金・助成金7選を詳しくご紹介します。
補助金・助成金を受給するまでの流れや注意すべきポイントも解説するため、ぜひ参考にご覧ください。

目次
建設業者が利用できる補助金・助成金の概要


補助金と助成金は、政府が企業や個人に対しておこなう資金の給付です。
支給条件に違いがあり、補助金は支給条件を満たして審査に通過した人に支払われます。
補助金の申請には「事業計画書」を提出する必要があり、審査を通過し予定通りに事業計画が完了していれば受給できます。
一方助成金は、助成金の要件を満たしていれば、受給できる可能性が高いものです。
申請期間も長いため、余裕を持って申請できる点が特徴です。
補助金や助成金は種類によって公募要領が異なるため、申請項目をチェックしてから申請手続きをおこなうようにしましょう。
【2024】建設業者におすすめの補助金・助成金7選


こちらでは、建設業者におすすめの補助金・助成金を7つご紹介します。
各制度の詳細や特徴について詳しく説明するため、ぜひチェックしてください。
補助金や助成金の概要について知りたい方は、下記の表を合わせてご覧ください。
| 補助金・助成金の種類 | 概要 |
|---|---|
| 働き方改革推進支援助成金 | 中小企業の生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備を支援する補助金 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者が制度変更に対応するための経費を補助する補助金 |
| 中小企業省力化投資補助金 | 中小企業等の売上拡大や生産性向上に必要な省力化投資を促進する補助金 |
| 業務改善助成金 | 生産性向上に必要な設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成 |
| 人材確保等支援助成金 | 労働環境の向上を図る事業主・事業協同組合等を補助する助成金 |
| トライアル雇用助成金 | 就職が難しい求職者を対象に一定期間試行雇用をおこなう事業者への助成金 |
| 人材開発支援助成金 | 事業主が雇用する労働者に専門的なノウハウを習得させるために実施した訓練経費の一部を補助する助成金 |



1.働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金は、中小企業の生産性を向上させるための支援をおこなう助成金です。
時間外労働の削減や年次有給休暇・特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の支援を目的した助成金です。
建築業者の場合、対象者は労働者災害補償保険の適用事業主であり、資本金が3億円以下または300人以下である必要があります。
助成額は最大730万円となっており、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
支給までの流れとして、厚生労働省が定めている締め切り期日までに交付申請書を申請窓口へ提出、取組み実施後に支給申請書を提出します。
2.小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が制度変更に対応するための経費を補助する補助金です。
小規模事業者を対象としており、企業の働き方改革やインボイス導入に対応する取り組みの経費を一部補助できます。
建築業者の場合、対象者は常時使用する従業員の数が20人以下で、事前に必要書類等を地域の商工会・商工会議所の窓口に提出の上、「事業支援計画書」の作成・交付を受ける必要があります。
支給額は50万円〜200万円となっており、1つの枠のみ申請が可能です。
インボイス特例の要件を満たしている場合、補助上限額を50万円上乗せできます。
支給までの流れとして、全国商工会連合会の電子申請システムから受付締切までに申請手続きをおこないましょう。
3.中小企業省力化投資補助金
中小企業省力化投資補助金は、中小企業等の売上拡大や生産性向上に必要な省力化投資を促進する補助金です。
人材不足の課題を解決するためにIoTやロボット等の導入支援をおこない、付加価値額や生産性向上を図りながら賃上げにつなげることが目的です。
人手不足の状態にある中小企業が対象となっており、建築業者の場合、対象は資本金が3億円以下、または従業員数が300人以下となります。
中小企業省力化投資補助金サイトのカタログに記載された製品が補助対象となります。
従業員数はカタログに記載された製品によって、5名以下、6〜20名、21名以上の3種類に分類されます。
支給額は200万円〜最大1,500万円となっており、補助率は2分の1以下です。
支給までの流れとして、GBizIDを取得して導入製品の選定、補助金の交付申請、補助事業の実施・精算、実績報告、効果報告を行う流れです。
詳しくは中小企業省力化投資補助金サイトの中小企業省力化投資補助金の申請フローを参考にご覧ください。
4.業務改善助成金
業務改善助成金は、生産性向上に必要な設備投資の一部を支給する助成金です。
機械設備やコンサルティング導入などの投資に利用でき、発生した費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い金額を助成可能です。
中小企業・小規模事業者が対象となっており、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であれば申請できます。
建築業の場合、資本金または出資額が3億円以下、従業員が300人以下であれば対象となります。
支給額は、引き上げる最低賃金額と労働者の人数によって変動するシステムです。(事業場内最低賃金を30円以上引き上げる必要があります)
例えば引き上げる最低賃金額が30円以上の場合、30万円〜130万円までが上限額となっています。
支給までの流れとして、交付申請書と事業実施計画書を作成・提出して計画に基づいた事業を実施します。
詳しくは厚生労働省サイトの業務改善助成金の手続きを参考にご覧ください。
5.人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金は、労働環境の向上を図る事業主・事業協同組合等を補助する助成金です。
人材の確保・定着を目的としているため、安定した従業員の獲得を目指す企業に最適です。
8つのコースが用意されており、建設業では「建設キャリアアップシステム等普及促進コース」や「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)」などがあります。
「建設キャリアアップシステム等普及促進コース」は建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録費用等の一部の補助が受けられます。
「若年者および女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)」は教育訓練・研修等の費用の一部補助が受けられます。
支給までの流れとして、計画届と支給申請書を作成・提出して管轄労働局の確認後に支給される流れです。
詳しくは厚生労働省サイトの建設事業主等に対する助成金 支給要領を参考にご覧ください。
6.トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、就職が難しい求職者を対象に一定期間試行雇用をおこない補助する助成金です。
求職者の早期就職や雇用機会の創出を目的としており、建設現場の人材確保に活用できます。
このうち、「若年・女性建設労働者トライアルコース」は、35歳未満もしくは女性を対象労働者としており、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間の助成金が支給されます。
雇入れの場合、支給対象期間中の月額合計額がまとめて1回で支給されます。
支給までの流れとして、トライアル雇用実施計画書と支給申請書の作成・提出して審査通過後に支給される流れです。
詳しくは厚生労働省サイトを参考にご覧ください。
7.人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に専門的なノウハウを習得させるために実施した訓練経費の一部を補助する助成金です。
労働者の知識・技術の習得を目的としており、人材のスキルアップに活用できます。
建設業では、「建設労働者認定訓練コース」や「建設労働者技能実習コース」などを利用できます。
雇用する有期契約労働者に職業訓練を実施する事業主が対象となっています。
訓練経費の助成と賃金助成があります。
支給までの流れとして、経費助成は認定訓練終了後に支給申請を実施、賃金助成は、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受け、その申請期間内に、必要書類一式を作成・提出して審査通過後に支給される流れです。
詳しくは厚生労働省サイトの人材開発支援助成金を参考にご覧ください。
建設業が補助金・助成金を支給するまでの流れ


建設業が補助金・助成金を支給するときは、以下の流れとなっています。
支給要件のチェック
補助金や助成金には、それぞれ支給要件が設定されています。
支給要件は補助金や助成金を受け取るための条件となっており、申請前に項目をチェックしておく必要があります。
支給要件は細かく条件が設定されているため、内容を確認していなければ審査に通過できません。
制度によっては通常枠やグローバル枠などの種類があり、 特定の枠で申請できることもあります。
まずは申請を検討している補助金・助成金の支給要件をチェックし、条件を満たしているか整理するようにしましょう。
提出書類の準備
支給要件の条件を満たしたら、提出書類を準備します。
提出書類の準備には2週間〜3週間ほどかかるため、提出期限に間に合うよう余裕を持たせて進めることが大切です。
補助金の場合、申請期限前でも予算上限に達すると受付が終了することがあるため注意が必要です。
書類提出・審査
提出書類の準備を終えたら、提出をして審査結果を待ちます。
補助金や助成金によって書類の提出方法は異なるため、指定の方法でおこなう必要があります。
最近では電子申請が主流となっており、パソコンやスマートフォンから手軽に書類を提出することが可能です。
官公庁主催の制度は電子申請、地方自治体主催は郵送申請が多い傾向にあります。
郵送申請の場合、提出には「当日消印有効」と「締め切り当日必着」があるため注意してください。
書類の審査には1ヶ月以上かかることもあるため、締め切りを考慮しながら事業を進めるようにしましょう。
事業の進行
書類提出によって審査に通過すると、採択通知が届きます。
採択通知が届いたら、計画書に従いながら事業を進めていきます。
申請した補助金や助成金によって事業内容は異なりますが、システム・ITツールの導入や研修制度の実施などをおこなう流れです。
計画書通りに事業が進んでいない場合、補助金や助成金を受け取ることはできません。
完了報告の提出
計画書に従って指定の事業を終えたら、完了報告書を提出します。
完了報告書を提出しなければ補助金・助成金は支給されないため、早急な対応が求められます。
また、計画書通りに事業が進まなかった場合、支給額の減額や採択取消しになる可能性も高いです。
そのため計画書を細かくチェックし、指定の事業を終えたら速やかに完了報告書を提出しましょう。
補助金・助成金の支給
完了報告書を提出後、再審査によって承認されると補助金・助成金が支給されます。
補助金や助成金の支給期日が通知されるため、当日に登録口座をチェックしてください。
建設業者が補助金・助成金を利用するときに注意すべきポイント


建設業者が補助金・助成金を利用するときは、以下のようなポイントに注意しましょう。
支給率は100%ではない
補助金や助成金は、審査に通過して採択通知を受け取ったとしても必ず支給されるわけではありません。
計画書の提出が求められる場合、計画通りに事業が進んでいなければ減額や採択取消しになることもあります。
審査通過後にすぐ支給される補助金・助成金もありますが、計画書の提出が必要であれば事業の完了報告書を提出しなければなりません。
もし審査に通過しやすくするために完了が難しい計画書を作成してしまうと、スムーズに事業が進まず採択取消しになる恐れがあります。
書類不備に気をつける
補助金や助成金を申請するときは、書類不備に気をつけましょう。
書類不備があった場合、事務局から修正の問い合わせがあります。
書類の修正には時間と手間がかかるため、提出期限が迫っているときは注意が必要です。
もし経営者だけで書類の作成が難しいと判断したときは、補助金や助成金に詳しい専門家に相談することも1つの手段です。
専門家に相談するときは、対応実績のある信頼性が高い相手を見つけるようにしましょう。
実施前の申請が必要
ITツール・システムの導入や賃金引き上げなどは、補助金・助成金の交付が決定してから実施するようにしましょう。
決定前に建築機械を導入したりコンサルティング依頼をしたりすると、補助金・助成金の対象外となってしまいます。
ただし、制度によっては交付決定前に実施が認められているケースも存在します。
補助金や助成金は申請期間が定められているため、申請のタイミングを間違えないように注意しておきましょう。
まとめ
今回は、建設業で利用できるおすすめの補助金・助成金7選、支給するまでの流れ、注意すべきポイントまで詳しくご紹介しました。
補助金や助成金は、建設業のITツールの導入や効率化への試みを支援するためのものです。
ぜひ当記事でご紹介した方法を参考にしながら、補助金や助成金の申請をはじめてください。
建築現場博士がおすすめする工務店・建築業界の業務効率化ソフトはAnyONEです。
導入実績2,700社超の業界No.1基幹システムで、国交省「第一回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択されています。
エクセルのような操作感で、レイアウトもマウスで変更できるため、ITが苦手な方でも簡単にお使いいただけます。
また、システムの導入後も徹底的なサポートを受けられるため、安心して運用できるでしょう。
大手・中堅企業様から一人親方様まで規模感を問わず、業務状況に合わせて様々な場面でご利用いただけます。






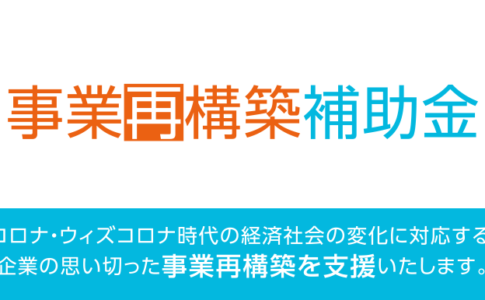
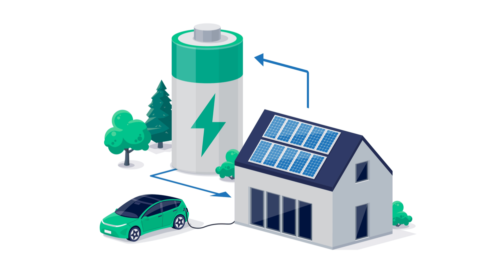








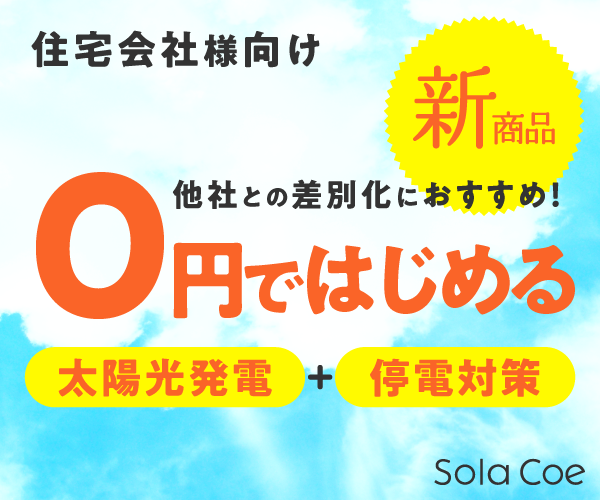
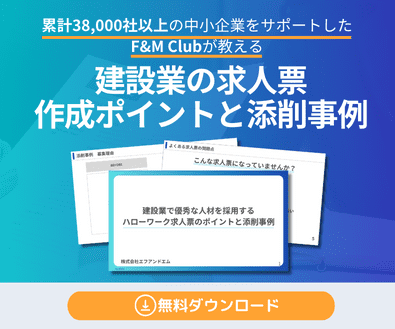



コメントを残す