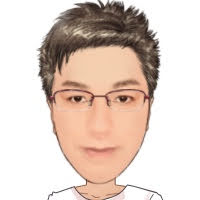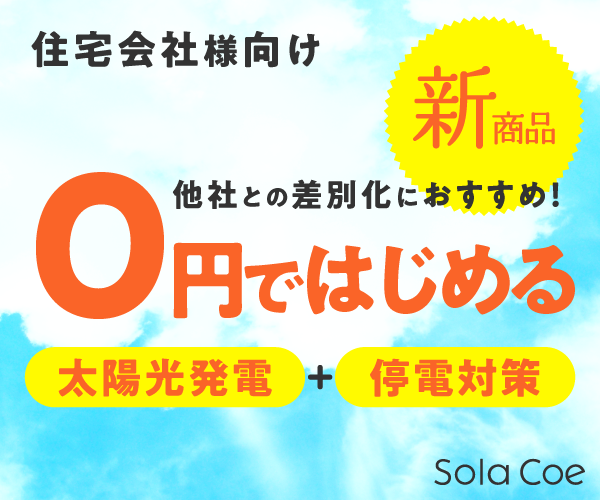建築会社では、施主から内装工事を依頼されることもあります。
内装工事は施主の要望に合わせて仕上げる必要があるため、状況に合わせて対応しなければなりません。
当記事では、内装工事の詳細から工事内容の種類、具体的な業務手順までわかりやすく解説します。
内装工事とは

内装工事とは、建物内の設備・装飾の施工のことです。
工事の詳しい内容や目的について理解し、内装工事に対応しましょう。
内装仕上工事
内装仕上工事は、施主の要望に合わせて作成した設計図をもとに建物内の壁・床・天井などを作り上げていく工事です。
内装仕上工事では、建物内の骨組みや基礎、下地などを作りながら壁紙やフローリングなどの材料で仕上げをおこない、必要に応じて塗装もおこないます。
ドアや窓など内装に合わせた建具・家具の組み立て・作成も内装仕上工事のひとつです。
内装仕上工事によって建物を設計通りの間取りにし、施主の求めるデザインに仕上げます。
設備工事
設備工事は、電気やガス、水道、空調など建物内で利用する設備を使えるようにする工事です。
内装工事の定義は住宅用と事業用において異なります。住宅用の内装工事は『内装仕上工事』のみを意味し、事業用の場合は内装だけでなく、設備工事を含みます。
電気やガス、水道だけでなく空調の設備が問題なく使用できるようにします。
内装工事の目的
内装工事の目的は、施主の要望に合わせて機能的で美しい仕上がりにすることです。
住宅の内装工事をおこなう場合、家族の安全性や過ごしやすさなどを考慮しながら建物内を作り上げていきます。
店舗やオフィスの場合は快適性や機能性を重視した内装に仕上げ、内装によって商材の魅力を高めたり従業員のモチベーション・業務効率を向上させることが目的です。
どのような建物を内装工事するかによって目的は異なるため、施主とのヒアリングを通じて明確にしながら工事を進めていきましょう。
美観・機能向上・耐久性向上・法規制対応
内装工事では、美観や機能、耐久性、法規制などのポイントを意識して取り組む必要があります。
建物利用者のことを考え、美しく機能的で耐久性に優れている仕上がりにすることが大切です。
また、内装工事をおこなう際には内装制限についても忘れてはいけません。
内装制限とは、火災時に避難経路を確保するため、内装材に不燃・準不燃などの性能を求める規定です。
なお、建物が防炎防火対象物の場合は、消防法に基づいて「消火設備」「警報設備」「避難設備」の3つの消防設備の設置が定められるなど、さまざまな制限があります。
そのため施工業者は施主からの要望に応えながら、内装制限に従った内装作りができるかチェックしておかなくてはいけません。
建築工事との違い
建築工事とは、住宅やマンション、ビルなどの建築物を建てる工事です。
内装工事は建物内部のみの工事であり、建築工事とは工事業者も違うケースが多いです。
建築工事では、新築工事や増築工事、改築工事など建物の基礎構造設計から全般の建築をおこないます。
このように建築工事と内装工事は工事内容に違いがあるため、施主に説明する際は正しく伝えるようにしましょう。
リフォームとの違い
リフォームとは、老朽化した建物を新築の状態に戻す工事です。
建物は年数が経過すると、壁紙や床の張替え、雨漏りなどの修繕、外壁や屋根の塗り替えなどが必要となります。
リフォームは既存の設備をベースとしており、1から作り上げる内装工事とは工事方法が異なります。
規模や目的が異なり、内装工事は建物の内部を仕上げる工事、リフォームは建物の機能や構造を改善する工事として理解しておきましょう。
内装工事の種類

前述では、内装工事に内装仕上工事と設備工事の2種類があると説明しました。
内装仕上工事と設備工事にはさまざまな工事方法があるため、内容について理解を深めておくことも大切です。
それでは内装仕上工事と設備工事の工事方法を詳しく紹介します。
内装仕上工事に含まれる工事
こちらでは、内装仕上工事に含まれる工事方法について説明します。
ぜひ参考にご覧ください。
軽鉄工事
軽鉄工事は、軽量鉄骨を使用して建物の天井や間仕切り、壁などの骨組みを作る仕事です。
水や湿気に強く、燃える心配もないため木材よりも耐久性に優れています。
レイアウト図に基づいて墨出しをおこないながら、骨組みを立てる流れが基本的な施工手順です。
工事単価も安く抑えることができ、内装工事の現場で使用されるケースが多いです。
室内の区切りや間仕切りをおこない際にも、軽鉄工事の骨組みから間仕切り壁を造ります。
工期の短縮や自由な部屋の区切りができることから、メリットの多い工事方法となっています。
ボード工事
ボード工事は、天井や壁に石膏ボードを貼って下地を作る工事です。
石膏ボードだけでなく、プラスターボードや木質ボードなどが用いられるケースも多いです。
石膏ボードなどの板には断熱・防音・耐火などの役割があり、さまざまな機能や種類があります。
建物の特性や用途に合わせて、適切な素材を選択して施工します。
軽天の上にボードを貼り付けながら、パテで境目を埋める流れが基本的な施工手順です。
音漏れ対策が必要な建物では、ボード工事をおこなうことで音を遮断できるようになるでしょう。
クロス工事
クロス工事は、ボードや合板などの上にクロス(壁紙)を貼っていく工事です。
住宅だけでなく、店舗やオフィスなどの内装工事にも用いられています。
落ち着きのある色や明るい色など、施主の要望に合わせて壁紙を変更できます。
クロス工事をおこなうことで、店舗や企業のイメージを表現し、統一感を出すための工事です。
ボードの継ぎ目があるとクロスを貼ったときに凸凹ができやすいため、クロス工事前に下地を平らにすることが大切です。
クロス工事の素材には、ビニール、布、紙、プラスチックなどが使われます。
防音、消臭、防カビ、防汚、抗菌など多くのメリットがある点も特徴です。
壁紙の寿命は一般的に10年程度となっており、張り替えによって綺麗な状態を保てます。
塗装工事
塗装工事は、建物内の壁・床・天井などを塗装する工事です。
塗装工事の塗料は顔料や油類、合成樹脂、添加剤、溶剤などで構成されており、防水処理などの機能性を持たせられます。
新築から10年が経過したり、塗膜の劣化が著しかったりするシーンで塗装工事をおこなうことが多いです。
塗の種類には自然塗料やAEPなどがあり、目的に合わせて使い分けます。
建物内の色にこだわることもできるため、企業や店舗のイメージに合った塗装が可能です。
左官工事
左官工事は、壁や床などにモルタルや土壁などの材料を使用して塗り固める工事です。
「こて塗り」や「吹付け」などの方法があり、専用のコテを使って塗り固めていきます。
クロスやタイルの貼り付け前には、凸凹をなくすために左官工事をおこなうケースもあります。
専用のコテによって壁の模様や質感にこだわりを持たせられるため、こだわりのある内装に仕上げることが可能です。
床仕上げ工事
床仕上げ工事は、床材を使って床面の仕上げをおこなう工事です。
フローリングやクッション、フロアカーペット、塩ビタイルなどの素材を使用することで床面を仕上げていきます。
もともと敷かれていた床を交換する場合も、同じく仕上げ工事をおこないます。
床の高さ調節や空気の通り道の確保なども床仕上げ工事の1つです。
機能性と見た目の美しさを両立できる床材を使用し、きれいな状態へと仕上げていきます。
木製・金属建具工事
木製・金属建具工事は、木製もしくは金属製の建具を設置する工事です。
建具とは、ドアや窓など開口部に設けられる開閉機能を持つ仕切りを指します。
ふすまや障子なども木製・金属建具工事に含まれており、内装工事後の仕上げにおこなわれます。
最近ではデザイン性の高い建具が増えたことから、企業や店舗のイメージに合わせた建具の取り付けが可能です。
畳工事
畳工事は、畳に関連する工事全般を指します。
例えば、畳を全て新調する「新畳工事」や古い畳のい草を新しくする「畳張替え工事」などです。
飲食店などでは畳を使った部屋が設けられることもあるため、畳工事が必要になるケースもあります。
畳工事をおこなえば、もとから設置されている畳の使用や新たな畳の設置が可能です。
大工工事
大工工事は、大工職人が木材を加工したり取り付けたりして家具を制作する工事です。
店のデザインに合わせて棚や椅子などを製作してもらえるため、企業や店舗のイメージに合わせられます。
現場で家具を製作するため運搬コストを抑制できる点がメリットです。
ただし、複雑なデザインは現場での加工が難しいため、難しい家具の製作は専門の家具工事が必要です。
家具工事
家具工事は、室内の造りに合わせて造作家具を作成・設置する工事です。
内装デザインやスペースに合わせた家具を設置できるため、理想的なかたちに仕上げられます。
すでにパーツや家具が完成した状態となっているため、施工業者は組み立てや設置のみの作業で済ませられます。
設備工事に含まれる工事
こちらでは、設備工事に含まれる工事方法について説明します。
内装仕上工事と合わせてチェックしてください。
電気工事
電気工事は、建物内で電気を使えるようにする工事です。
分電盤やブレーカーなどの設置、コンセントの配線・設置、Wi-FiのLAN配線、防犯カメラの配線・設置などが主な内容となります。
LANやWi-Fi等の弱電設備は電気工事と分けて設計・発注されることもあります。
電源周りの工事だけでなく、照明の取り付けやテレビ・パソコンの設置なども電気工事の対象です。
ガス工事
ガス工事は、建物内でガスを使えるようにする工事です。
住宅や飲食店などの建物では、配管の敷設やガスメーター、安全弁の設置などが主な内容となります。
住宅や飲食店だけでなく、給湯器などを使用する業種では同じくガス工事が必要です。
ガス漏れ検知器の設置もガス工事に含まれるため、ガス周りの業務全般をおこないます。
給排水設備工事
給排水設備工事は、建物内で水を使えるようにする工事です。
給水・排水に必要な配管の敷設や、厨房機器・手洗い場・洗濯機などへの接続配管、グリーストラップの設置などが含まれます。
また、建物内の排水系統から屋外の排水桝までの範囲も施工対象となります。
空調設備工事
空調設備工事は、エアコンを設置して使えるようにする工事です。
機器の設置や配管など、エアコンの設置に関する作業は全て空調設備工事に含まれます。
そのため、すでに設置されているエアコンについても、空調設備工事の対象です。
換気設備工事
換気設備工事は、特定の場所で換気設備を設置する工事です。
厨房やトイレの換気扇、屋内の空気を排出する排気ダクトの設置が主な内容です。
焼肉屋や喫煙ブースなど、外に空気の排出が難しい箇所への換気システムや脱臭装置の設置も換気設備工事でおこないます。
内装工事の流れ

内装工事の基本的な流れは、以下の通りです。
1.施主との打ち合わせ
まずは施主と打ち合わせをしながら、内装工事の目的とコンセプトを明確化します。
店舗をおしゃれに仕上げたい、顧客に自社イメージを伝えたいなど内装工事を予定している施主にはそれぞれ目的があります。
施主によってはイメージが固まっていないケースもあるため、打ち合わせから1つずつ整理していくことが大切です。
2.設計・デザインプランの提案
内装工事の目的とコンセプトが決まれば、設計やデザインについて打ち合わせをします。
実現するための工事内容やデザイン案を提案し、施主から承諾を得ていきます。
施主の要望を聞きながら、最適な設計やデザインプランを提案するようにしましょう。
3.見積もりの提示・契約
続いて、内装工事に必要な費用について見積もりを提示します。
工事開始前の段階で費用を説明していなければ、施主とトラブルが発生する原因になるため注意が必要です。
提示した費用に承諾してもらうことができれば、施主と契約を締結します。
契約内容に問題がないか施主に再チェックしてもらい、記載事項にミスがないようにしましょう。
4.工事開始
施主との契約締結後、内装工事を開始します。
工事前には施主へ工程表を送ることで、現在の進捗状況について把握してもらいます。
工事途中に施主から調整や変更したい箇所の要望があれば、柔軟に応えるようにしましょう。
5.什器・設備の搬入
内装工事終了後、依頼通りの仕上がりになっているか施主に一度チェックしてもらいます。
問題がなければ、什器や設備を搬入します。
引渡し後に什器・設備の搬入をおこなうケースもあるため、施主との話し合いから決めるようにしておきましょう。
6.引渡し・アフターサービス
最後に施主へ引渡しとなれば、内装工事の工程は終了です。
内装工事の施工期間は1ヶ月〜2ヶ月程度が一般的です。
また、アフターサービスを設けており、一定期間内は施主からの悩み相談や追加作業などをおこないます。
以上が内装工事の基本的な流れです。
内装工事の費用

施主に内装工事の費用を説明するためにも、具体的な費用相場を理解しておくことも大切です。
内装工事の費用は、主に坪単価で計算されます。
10坪の店舗であれば内装工事費用は300〜500万円程度、30坪なら600〜1,500万円程度が相場です。
こちらではスケルトン物件と居抜き物件の費用相場について説明するため、ぜひチェックしてください。
スケルトン物件
スケルトン物件とは、内装や設備が撤去された状態の物件であり、居抜き物件と比べて内装工事や設備工事に費用がかかります。
例として、用途ごとの費用相場を紹介します。
| 用途 | 坪単価の相場 |
|---|---|
| オフィス | 20万円〜40万円程度 |
| カフェ・飲食店 | 50万円〜80万円程度 |
| 美容院・サロン | 40万円〜70万円程度 |
居抜き物件
居抜き物件とは、前テナントが使用していた設備や内装、什器などが残っている物件です。
スケルトン物件と比べて初期費用を抑えられ、工期も短いです。
ただし設備の老朽化や業態の違いによってはむしろ割高になるケースもある点に注意しましょう。
居抜き物件の内装工事の費用相場も、以下のように用途によって異なります。
| 用途 | 坪単価の相場 |
|---|---|
| オフィス | 10万円〜30万円程度 |
| カフェ・飲食店 | 30万円〜60万円程度 |
| 美容院・サロン | 20万円〜50万円程度 |
内装工事をおこなうときの注意点

内装工事をおこなうときは、以下のような点に注意してください。
近隣住民に挨拶や告知をおこなう
内装工事の開始前には、近隣住民に挨拶や告知をおこなうことが大切です。
内装工事では騒音や匂い、車両の問題などがあるため、挨拶や告知をしなければクレームが発生する原因となります。
効率良く告知をおこなうには、手紙や張り紙が有効です。
近隣住民からの理解を得るためにも、必ず内装工事の開始前には挨拶や告知をおこないましょう。
追加費用が発生する可能性を説明しておく
内装工事は建物の大きさや状態、業種によってかかる費用が異なるため、見積もりを出していても追加費用が発生する場合があります。
また、施主から工事開始後に追加の要望があれば、同じく追加費用がかかる点も説明が必要です。
最終的な金額の提示前に追加費用を伝えておくことで、施主とのトラブルを防止できます。
何にどれくらいの費用が必要になるのかを具体的に説明し、施主から理解してもらうようにしましょう。
騒音を防ぐ取り組みをおこなう
内装工事で騒音を防ぐには、吸音材や遮音材、防振材などを活用したり作業の工程を見直したりすることが有効です。
壁や天井に吸音パネルや遮音シートを貼り、間仕切り壁に吸音効果の高いグラスウールなどを充填することで内装工事の騒音を防止できます。
また、工事中には窓を閉めておくことで、内部の作業音を軽減できます。
騒音は近隣住民からのクレームにつながるため、防ぐための取り組みをおこないましょう。
まとめ
今回は、内装工事の詳細から工事内容の種類、具体的な業務手順までわかりやすく解説しました。
内装工事は建物内の設備・装飾の施工であり、内装仕上工事と設備工事の2つの工事があります。
美観や機能、耐久性、法規制などのポイントを意識して取り組むことで、施主に満足してもらえる仕上がりとなります。
住宅や店舗、オフィスなど、建物によって目的やコンセプトは異なるため、施主とのヒアリングを通じて内装工事を進めることが大切です。
ぜひ当記事で紹介した工事内容や方法を参考にしながら、内装工事の施工を取り入れてください。
建築現場博士がおすすめする工務店・建築業界の業務効率化ソフトはAnyONEです。
導入実績2,700社超の業界No.1基幹システムで、国交省「第一回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択されています。
エクセルのような操作感で、レイアウトもマウスで変更できるため、ITが苦手な方でも簡単にお使いいただけます。
また、システムの導入後も徹底的なサポートを受けられるため、安心して運用できるでしょう。
大手・中堅企業様から一人親方様まで規模感を問わず、業務状況に合わせて様々な場面でご利用いただけます。